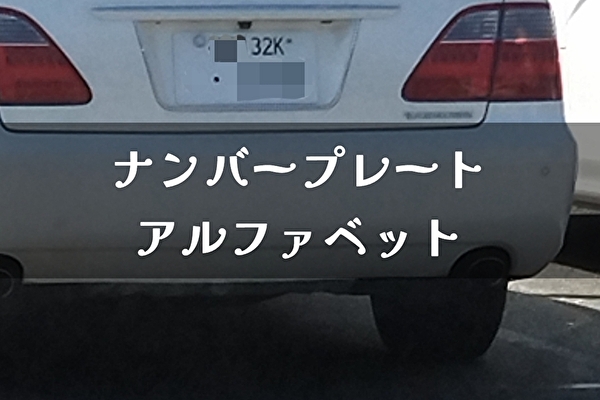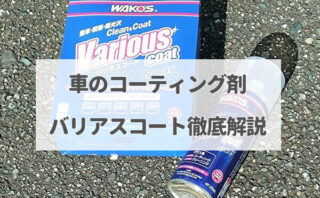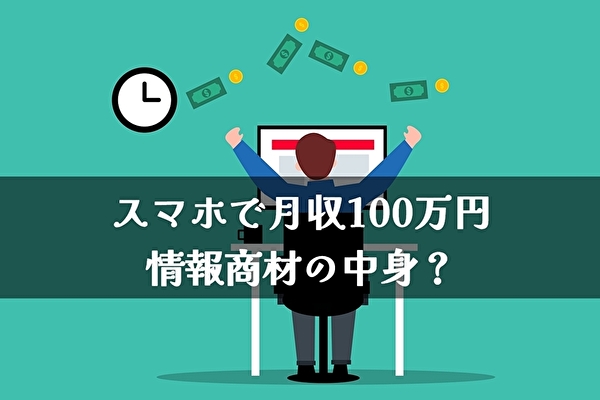最近少しづつ増えているのが、アルファベットが入った車のナンバープレートです。
今までは、数字・地域名(都道府県)・ひらがなでした。
最近は、これにアルファベットまで、記載されているナンバープレートもあるんです。

この車のナンバープレートには「32K」と記載されています。
これはどういう意味なのでしょうか?
まずは、ナンバープレートの記載内容をご説明します。
ナンバープレートの見方

日本のナンバープレートのサイズは:330×165mm
上部…「地域名」と「3桁の分類番号」
下部左…「ひらがな1文字」
下部右…「4桁の一連指定番号」
ナンバープレートの歴史
日本のナンバープレートは何度も変更されてきました。
昭和20年代には、横長の欧州のナンバープレートのような形で発行されことがあるものの、昭和30年代には現在とほぼ同じ形に統一されています。
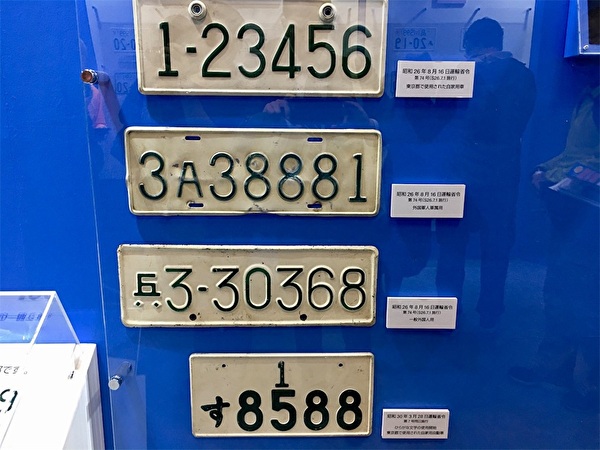
写真の上の3枚のナンバープレートは、昭和20年代で、下は昭和30年のナンバープレートです。
日本は分類番号が「1桁(1950年代以降)」→「2桁(1967年以降)」→「3桁(1997年以降)」に変更されてきた歴史もあります。
ご当地ナンバー
最近はオリンピック・パラリンピック・ラグビーワールドカップにちなんだ「図柄が入ったナンバープレート」がありました。
さらに、「ご当地ナンバー」も2018年に導入されました。

ご当地ナンバー人気ランキング→こちら
アルファベットの導入
ナンバープレートのニュースとしてもうひとつ挙げられるのが、「分類番号へのアルファベットの導入」です。
「分類番号」の3桁のうち、下二桁にアルファベットを表記できるようにするものです。
これは2017年1月に国土交通省が施行したもので、2018年1月から実際にナンバー交付されています。
なぜ、こんな制度が必要になったのか?
1999年にはじまった希望番号制度の普及により、いくつかの数字に人気が集中したためです。
誕生日や記念日などに由来する数字であれば、まだ在庫に余裕はありますが、地域によって「・・・1」や「・・・8」などは、抽選となり、事態は切迫していました。
そこで、アルファベット26文字の中から「A」や「C」、「F」など10文字を選択、分類番号の下ふた桁に導入できるように制度を変更。
ちなみに、B(ビー)やI(アイ)、O(オー)など16文字のアルファベットは、数字と混同する恐れもあるため欠番となっています。
アルファベット10文字
導入されたアルファベットは「A・C・F・H・K・L・M・P・X・Y」
この分類番号を指定することはできません。